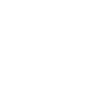 代謝異常で起こる病気
代謝異常で起こる病気
肥満症
ひまんしょう
Obesity
初診に適した診療科目:内科
分類:代謝異常で起こる病気 > 肥満症
広告
広告
どんな病気か
肥満とは単に体重が多いことではなく、脂肪組織が過剰に蓄積した状態のことです。しかし、体内の脂肪組織の量、すなわち体脂肪を正確に測定する方法は簡単ではないので、身長、体重に基づく指数が肥満の基準として用いられてきました。
最近、体脂肪計として市販されているものは、生体インピーダンス法といって、微弱な電気を人体に流して体脂肪量を計算するものですが、その正確性はまだ不十分です。
肥満自体は病気ではありません。体脂肪は、エネルギー補給機能、体温を維持するための断熱作用、内臓の保護作用などのよい役割ももっています。しかし、肥満があるとさまざまな健康障害(合併症)を起こしやすいことが問題です。肥満に基づく健康障害を合併した場合や、その危険が高い場合を「肥満症」といいます。
最近の研究から、肥満の合併症は肥満度が高いことのみで起こるのではなく、むしろ内臓脂肪が蓄積する「内臓脂肪型肥満(上半身肥満)」で起こりやすいことがわかってきました。くわしくは後述します。
●標準体重と肥満度
「標準体重」とは、その身長における最も生理的な状態にある場合の体重を意味します。また、その体格における死亡率が最も低い体重という意味で「理想体重」という表現が用いられることもあります。従来、日本では「(身長‐100)×0・9㎏」で求めるブローカ・桂変法による標準体重の計算が用いられていましたが、これは簡便ではあるものの誤差が大きいなどの欠点がありました。
そこで日本肥満学会は、「体重(㎏)÷身長(m)の二乗」で計算されるボディマス指数(BMI)が22の時に病気の合併率が最も少ないという統計成績に基づき、「身長(m)の2乗×22」によって求められる体重を、標準体重とするよう勧告しました。このように計算された標準体重は、厚生労働省(旧厚生省)の「日本人の肥満とやせの判定表」の数字ともよく合っています。
標準体重に基づいて、肥満度は「(体重‐標準体重)÷標準体重×100%」で計算されます。この式によれば、標準体重よりも少ない体重の人は肥満度がマイナスで表されます。
肥満の判定基準は、従来、肥満度20%以上、BMI換算で26・4以上ということでしたが、日本肥満学会は肥満の判定基準をBMI25以上とすることを提唱しました。肥満およびやせの判定表を表17に示します。
原因は何か
●体重の調節メカニズム
体重は、エネルギーの摂取と消費のバランスで決定されます。エネルギーの摂取は食事によりもたらされ、エネルギーの消費は基礎代謝(体温の維持と呼吸や血液循環など生命の維持に使われているエネルギー)、食事摂取時の熱産生、生活活動や運動によるエネルギーによります。
成人では、このバランスが維持され、体重は変化しないように調節されています。すなわち、体重が減少すると食欲が亢進してエネルギーの消費は減少し、逆に体重が増加すると食欲が低下してエネルギーの消費は増加します。
最近、こうした調節にはさまざまな因子が関わっていることがわかってきました。そのなかで、食欲の調節には脂肪細胞から出るレプチンという蛋白質が重要な役割をしています。レプチンは脳の視床下部というところの満腹中枢にはたらいて食欲を抑えるはたらきがあり、レプチンがなくなった動物では著しい肥満になることがわかっています。
また、胃から産生されるグレリンという蛋白質が視床下部にはたらいて、レプチンとは逆に食欲を増進させることもわかってきました。「腹ぺこ」で食欲が出るしくみはグレリンによるものだったのです。
さらに、熱産生を行う蛋白質が新たに発見され、熱産生に伴う消費エネルギーの低下が肥満の原因のひとつになることから、注目されています。
●遺伝と環境
いろいろな病気が起こる原因には、遺伝と環境の両方が関わっています。肥満に関しても、人類の歴史のほとんどが飢餓と寒さとの戦いであり、獲得したエネルギーを脂肪として蓄える体の仕組みが発達した結果、いわゆる倹約遺伝子(肥満遺伝子)が保存されてきたと考えられています。
遺伝因子について世界中で研究が行われています。現在のところ、複数の遺伝子の関与が明らかになり、遺伝子を調べて肥満になりやすい体質かどうかをある程度判断できるようになってきましたが、高い確率で肥満を予測できるまでには至っていません。
一般には、肥満の原因としては環境因子のほうが重要と考えられています。環境因子としては、以下に述べる、食べすぎ(過食)、食べ方の誤り、運動不足が重要です。食べることに不自由がなく運動量が少ないという欧米型ライフスタイルが浸透するとともに、これらの環境因子は日本でも増加し、肥満が急激に増えています。
●食べすぎ
なぜ食べすぎになるのでしょうか。通常は、すでに述べたレプチンなどによって満腹中枢が刺激され、私たちは食べすぎないようになっています。
遺伝的にレプチンに異常があるために肥満が起こってくることはまれです。むしろ、肥満した人の多くではレプチンは増えていることがわかってきました。おそらく、レプチンのはたらき、あるいは満腹中枢の機能が障害されているものと考えられています。
食べすぎを引き起こすきっかけとしては、ストレスが重要と考えられています。強いストレス状態におかれると、手元にある食べ物を手あたり次第に食べてストレスを解消しようとする「気晴し食い症候群」といわれる状態がありますが、多くの肥満者が食べることでストレス解消を図っていることがわかっています。
さらに、食べすぎが続くと胃が大きくなって、たくさん食べないと満腹感が得られないようになることも問題です。さらに食べすぎて、肥満が進行する原因になります。
●食べ方の誤り
意外にも、肥満者のかなりの人は食べすぎではないことがわかっています。こうした場合、食べる量よりも食べ方が問題です。食事回数と肥満との関係をみてみると、食事回数が少ないほど太りやすいのです。
すなわち、朝食を抜いて夜に多く食べるなどの「かため食い」は、食べた栄養が吸収されやすく、過剰エネルギーをもたらすことで肥満につながりやすいのです。食事の回数が減ることで、食事摂取時の熱産生が減ることも原因と考えられています。
1日の摂取量の半分以上を夜に食べる「夜食症候群」も太りやすい食べ方です。夜は消化管の機能が活発になり、食べた物が貯蔵エネルギーになりやすいと考えられます。また、「早食い」もよくありません。満腹感を感じにくく不必要に食べすぎることになります。
●運動不足
運動不足では、消費エネルギーが低下してエネルギーが体のなかにたまりやすくなりますが、それよりもエネルギーを体のなかにためやすいという代謝状態をつくるほうが重要です。
すなわち、運動不足は、血糖値を下げるはたらきをもつインスリンというホルモンのはたらきを低下させて、血糖を正常に保つのに必要なインスリン量を増やしてしまいます。この時のインスリンは、血糖値を下げる力は弱まっているのに、脂肪をつくる作用は弱まっていないために、体のなかで余分なエネルギーを脂肪に変えることを促進することになります。
さらに運動不足は、筋肉量を減らし、安静にしていても体温を維持し生命活動を保つために使われる基礎代謝で使われるエネルギーを少なくしてしまいます。また、脂肪合成酵素のはたらきも高まるので、脂肪が体のなかでつくられやすくなります。
肥満のタイプ
摂取エネルギーから消費エネルギーを差し引いた過剰エネルギーが脂肪として蓄積され、脂肪細胞が増加あるいは肥大して太りすぎ(過体重)になります。小児期からの肥満では脂肪細胞が増加し、成人してからの肥満では脂肪細胞が肥大することが多くなります。
脂肪の分布は、上腕部、腹部、臀部〜大腿部の皮下の場合と、腹部の内臓周囲の場合とがあり、それぞれ「皮下脂肪型肥満」、「内臓脂肪型肥満」と呼ばれます。あるいは、体型から「上半身肥満(リンゴ型肥満)」と「下半身肥満(洋ナシ型肥満)」に分けられることもありますが(図12)、前者は内臓脂肪型肥満、後者は皮下脂肪型肥満にほぼ対応します。
肥満の症状と合併症
肥満の自覚症状として頻度の高いものは呼吸障害です。睡眠時に、いびきや10秒以上の無呼吸が頻繁に認められ(睡眠時無呼吸症候群)、日中の注意力障害、居眠りを起こしたりします。さらに重症になると、チアノーゼ(皮膚などが紫色になる)、多血症、右室肥大、右心不全などを起こすこともあります(ピックウィック症候群)。
また、過度の体重負担により、下肢の関節(股関節、膝関節)、腰椎が障害され、腰痛、下肢痛などを起こします。
さらに、肥満によりさまざまな健康障害を起こしやすくなります。2型糖尿病、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症・痛風、動脈硬化症(心血管障害、脳血管障害)、脂肪肝は肥満により2〜5倍合併しやすくなります。これらの合併症は、皮下脂肪型肥満よりも内臓脂肪型肥満のほうに起こりやすいことがわかっています。
内臓脂肪蓄積に基づいて複数の病気が集積した病態は、最近は「内臓脂肪症候群」あるいは「メタボリックシンドローム」と呼ばれており、動脈硬化から心筋梗塞などを起こしやすいものとして注目されています。こうしたことから、内臓脂肪型肥満はハイリスク肥満とも呼ばれています。日本でもメタボリックシンドロームは激増しており、警鐘が鳴らされています。
そのほかに、肥満に合併しやすいものとして、胆石、生理の異常(無月経、月経不順)などがあり、最近は悪性腫瘍(大腸がん、胆嚢がん、乳がん、子宮がん、前立腺がんなど)が合併しやすいといわれています。
極度の肥満の場合は、上腕部、腹部、大腿部に皮下脂肪の断裂による皮膚線条が現れることもあります。また、うなじや腋窩などに黒い色素沈着が現れることもあります(黒色表皮腫)。
検査と診断
肥満があるかどうかは見ただけである程度見当はつきますが、より正確な判定のためには、身長と体重を測定し、前述のボディマス指数(BMI)を算出します。日本肥満学会の基準では、25以上を肥満と判定します。
すでに述べたように、肥満があるだけでは病気ではありません。肥満に基づく健康障害を有するもの、あるいはその危険が高い場合を肥満症として区別します。
合併症の危険が高いハイリスク肥満である内臓脂肪型肥満のスクリーニングとして、立位、呼気時のへその位置での腹囲を測ります。日本肥満学会の基準では、男性では85㎝以上、女性では90㎝以上であれば、内臓脂肪型肥満の可能性が高いものとします。内臓脂肪を正確に測定するためには、へその高さで腹部CT検査を行い、内臓脂肪面積を計算します。100㎡以上であれば内臓脂肪型肥満と診断します(図13)。
また、簡便に体脂肪率を測定する方法として、生体インピーダンス法による体脂肪計による測定があります。男性は体脂肪率20〜25%以上、女性は体脂肪率30〜35%以上を、肥満の目安と考えてよいと思われますが、同じ器械でも計測する時間、飲食、運動、身体状況などによって計測値が変化する場合があり、注意が必要です。
なお、別の病気が原因で肥満が起こることがあり、二次性肥満と呼ばれます。二次性肥満の場合は、主としてもとの病気の治療が必要になるので、二次性肥満かどうかの検査が行われることがあります。
二次性肥満としては、クッシング症候群などの内分泌性肥満、ステロイド薬、抗うつ薬などの薬物使用による薬剤性肥満、視床下部の腫瘍などによる視床下部性肥満、遺伝性疾患に伴う遺伝性肥満などがあります。
治療の方法
二次性肥満に対しては、原因となっている病気の治療が中心になります。通常の肥満の治療の基本は、食事療法と運動療法です。薬物療法、外科療法は日本ではほとんど行われていませんが、補助的な手段として使われることがあります。
食事療法と運動療法は、いっしょに行うことが重要です。食事療法だけでは、途中から減量効果がなくなる「適応」と呼ばれる現象が現れやすく、挫折することが多いのです。この現象は生体防御機構のひとつと考えられており、減量に伴って基礎代謝で使うエネルギーが低下することが原因です。また、食事療法だけでは、脂肪ではなく大切な体のなかの構成成分が減ってしまうことにもなりかねません。
肥満の治療は長い期間にわたります。一時的に体重が減ることはあっても、その後の体重増加(リバウンドと呼ばれる)を起こすことが多く、理想的な体重を維持できる割合は非常に少ないのです。減量した体重を維持するためには、肥満の原因になった食習慣などの生活習慣を改善することが重要です。
具体的には、1日の食事の時間、内容、摂取状況などをくわしく記録して、肥満の原因となる食行動や習慣を明らかにします。同時に体重を1日に数回測定してグラフにして記入しておくと、問題となる食行動がわかりやすくなります。こうした方法は行動療法と呼ばれ、最近注目されています。
さらに、減量を行うにあたっては、無理のない治療目標を立てる必要があります。体脂肪を1㎏減らすためには、約7000kcalのエネルギーを減らすことが必要です。食事療法だけでは、1日にごはんを3杯減らしたとしても、2週間くらいかかる計算になります。よく減量できたように思っても、水分が抜けているだけの場合も多いのです。1カ月に1〜2㎏程度の減量が無理のないところです。
●食事療法
肥満症の治療では、食事療法がその中心的役割を占めます。ただし、摂取する食事内容だけではなく、食習慣にも注意を払う必要があります。また、運動療法と並行して行うことが必要であることは、前に述べたとおりです。
食事療法を行ううえで考えなければならないのは、健康に障害を与えないで体脂肪を減らすことです。無理な食事療法は体脂肪だけでなく、体のなかの蛋白質、骨量などを減らすことになります。そのために重要な事項は、①摂取エネルギーの設定、②栄養素の配分、③食習慣の改善です。
①摂取エネルギーの設定
体脂肪を減らすためには、摂取エネルギーを消費エネルギーより低く設定する必要があります。しかし、健康な日常生活を送るうえで必要なエネルギー摂取量があります。
糖尿病の食事療法のところでも述べましたが、1日の必要エネルギー量は、標準体重に身体活動強度に基づく必要エネルギー量をかけることで求められます。通常の仕事の人では、標準体重に25〜30kcalをかけたあたりが必要エネルギーとなり、それからさらに低く設定することで減量効果が得られることになります。
外来で行う、通常の日常生活での食事療法では、こうした減食療法として1200〜1800kcalの範囲で摂取エネルギーの設定を行うのが普通です。減量のために入院した場合には、医師の管理下で、さらに低いエネルギーでの食事療法を行うこともあります。
とくに肥満の程度が強い場合は、超低エネルギー食療法(VLCD)と呼ばれる、1日に200〜600kcalしか摂取しない半飢餓療法を行うこともあります。
②栄養素の配分
摂取エネルギーを抑えるためには、3大栄養素である糖質(炭水化物)、蛋白質、脂肪、およびビタミン、ミネラルについての適切な配分が必要です。
糖質は制限しすぎると、体の蛋白質や脂肪からエネルギーが急激に動員されるため、体蛋白質の減少やケトン体が血液中に増えることがあります。そこで、糖質は1日に100g以上とるようにします。ごはんなら軽く1膳くらいです。
逆に、糖質を過剰にとると、体のなかで脂肪になるので注意しましょう。過剰の糖質の約3割が脂肪として蓄積します。
蛋白質は、内臓、筋肉などの蛋白質でできている活性組織の萎縮を防ぐために、標準体重1㎏あたり1・0〜1・2gの摂取が必要です。
脂肪については、ビタミンA・D・E・Kなどの脂溶性ビタミンは脂肪といっしょに吸収されるので、1日に20gくらいの摂取が必要です。しかし、蛋白質食品を必要量とっていれば脂肪も十分に含まれているので、高脂肪食品をとる必要はありません。
ビタミン、ミネラルの不足は体の機能異常、疲労感を起こすので、必要量をとらなければなりません。そのためには、緑黄色野菜、豆類、乳製品を十分に摂取するとよいでしょう。
ダイエット中は、水溶性ビタミンの補給のために総合ビタミン剤を併用するのもひとつの方法です。また、便通を整えるために食物繊維を十分に摂取します。
③食習慣の改善
食事の量・内容だけではなく、食習慣を正しく改善する必要があります。1日3食の規則的な食事、かため食い・早食いの是正、1日の摂取量の半分以上を夜にとる夜食症候群の改善などです。
●運動療法
①運動療法の目的と効果
肥満の治療として運動療法を行うことのねらいの第1は、体脂肪を減少させることです。運動を行うと、脂肪組織に蓄積されていた中性脂肪が分解し、そこで生じた遊離脂肪酸が筋肉で効率よく利用され、体脂肪が減少することになります。
さらに、合併症を起こしやすい内臓脂肪型肥満にとって、運動はとりわけ効果があります。内臓脂肪は皮下脂肪に比べて、運動によって燃焼しやすいからです。
運動療法の第2の目的は、太りにくい体質をつくることです。運動によって、生命活動に最低限必要なエネルギーである安静時の基礎代謝が上昇します。
また、運動によりインスリンのはたらきがよくなり、糖尿病になりにくくなります。インスリンのはたらきがよくなることで、インスリンの分泌量が下がるので、インスリンによる体脂肪蓄積作用を軽くすることができます。さらに運動は、脂肪合成酵素のはたらきを抑えることで脂肪をたまりにくくします。
運動には、そのほかにも次のような効果があります。
・心肺機能の増強と筋力の増強により、体力と運動能力を向上します。
・骨のカルシウムを保持し、骨粗鬆症を予防します。
・脂質異常症や高血圧を改善し、動脈硬化を予防します。
・運動による爽快感とストレス解消が得られ、ストレスによる過食を防ぎます。
なお、狭心症や下肢の関節障害などがある場合は、運動を制限あるいは禁止したほうがよい場合もあります。疑わしい場合は、運動療法を始めるにあたってメディカルチェックを行って、主治医と相談することが必要です。
②運動療法の実際
運動療法によるエネルギーの消費自体は、それほど大きなものではありません。適度な運動は食欲を増進するため、食事療法を同時に行わないとかえって体重増加を招いてしまうことも少なくありません。
いろいろな運動の消費エネルギーは、糖尿病の運動療法のところ(表14)に示しましたが、体脂肪を減らすためには運動による消費エネルギーを、1日200〜300kcal程度とするのがよいでしょう。歩行(ウォーキング)では1時間くらいです。
先ほど述べた運動による体質改善作用は3日以内に低下するため、運動は週に3回以上、1日合計30〜60分行うのが望ましいと考えられます。
運動の強さは、最大限に体力を使った時の50%前後の強さがよいとされています。脈拍数でいうと1分あたり110〜130になるくらいの運動で、早足での歩行などがこれに相当します。しかし、運動習慣がない場合に、いきなり長時間早足で歩いたりすると、膝や足などを傷めることが多いので、徐々に運動を強くしていき、時間を延ばすようにします。
運動の時間がうまくとれない場合は、通勤で歩いたり、なるべく階段を使うなどの工夫で運動量を増やすようにします。歩数計をつけて1日に7000歩以上を目標にするのもよい方法です。
運動の種類には、歩行、ジョギング、自転車、水泳など全身を使う有酸素運動と、筋力トレーニングなどの無酸素運動がありますが、有酸素運動は脂肪を燃焼させる効果があり、体脂肪減少のためには無酸素運動より適しています。有酸素運動のなかでも、自転車、水泳、水中歩行などは、膝と足への負担が少なく肥満者に適しています。
運動をする時間はいつでもよく、空腹時のほうが体脂肪が分解しやすい利点があります。しかし、糖尿病の人でインスリンや糖尿病ののみ薬を服用している場合は、低血糖の用心のため、運動はなるべく食後1〜2時間に行うようにします。
病気に気づいたらどうする
どんな病気でも、早期発見、早期対策が重要です。肥満に気づいたら次のようなことに気をつけましょう。
●摂取エネルギーの計算を覚える
エネルギー計算は一見難しそうですが、慣れればそれほど難しくないことがわかります。『糖尿病食事療法のための食品交換表』(日本糖尿病学会編、文光堂発行)は減量のためにも役立ちます。自分が実際に摂取エネルギーを理解し、エネルギー制限を正しく実行できるようにします。
●食事のポイントをおさえる
食事の量だけではなく、その質も問題です。肉類には蛋白質だけではなく脂肪も多く含まれているので控えます。ハンバーグ、フライドチキン、揚げ物なども控えます。
一方、野菜は低エネルギーでビタミン、ミネラルや食物繊維を多く含むので、たっぷり食べます。ただし、ノンオイルのドレッシングはよいのですが、油を含んだドレッシングやマヨネーズは高エネルギーなので使わないようにします。
果物はビタミン、ミネラルや食物繊維を多く含みますが、含まれる果糖が脂肪に変わりやすいので、食べすぎないようにします。
調理あるいは盛りつけにも工夫が必要です。調理の際には、油や調味料は計量する習慣をつけ、おかずはなるべく薄味にします。味つけが濃いとごはんの食べすぎにつながります。
調理方法は、「炒める」「揚げる」よりも「ゆでる」「焼く」にしたほうが、エネルギー量が少なくなります。また、調理器具として、テフロン加工のフライパンを使うと油の量を減らすことができます。
盛りつけは、必ず1人分づつ分けて盛ります。大皿などからとるようにすると、自分が食べた分量がわからなくなり、人につられて食べすぎになりやすいのです。また、茶わんを小ぶりにして皿数を多くするといった工夫をすることで食事の充実感が得られ、食べすぎを防ぐことができます。
●食べ方の工夫をする
早食い、ドカ食いにならないように、ゆったりとした気分で食事を楽しみます。
食べる順番としては、まずスープなどの汁物、野菜類など、低エネルギーのものから食べ始めます。よくかんで、味わいながらゆっくりと食べるように心がけます。ゆっくり食べることにより満足感も得られ、過食を避けることができます。
また、主婦の場合、残り物を自分で食べてしまわずに、冷蔵庫にしまうなどします。
●間食、清涼飲料水は慎む
食間にだらだら食べる習慣を改めます。間食で食べるスナック菓子、せんべいなどは炭水化物や脂肪が多く高エネルギーなので、そうしたものを手の届くところに置かないようにします。
また、コーラ、ジュースのような清涼飲料水は糖質を多く含むのでとりすぎないようにして、なるべくお茶や水にします。
なお、最近「カロリーオフ」「低カロリー」の飲料が普及してきていますが、これらは100mlあたり20kcal以下であれば表示できるため、大量に飲用すれば肥満の原因となります。「カロリーゼロ」は100mlあたり5kcal未満と少ないですが、含まれている代用甘味料の害が完全にないとはいい切れないので、大量の飲用は控えたほうがよいでしょう。
間食はしないことが原則ですが、どうしても空腹になった場合は、コンソメスープなどの温かい飲み物をゆっくり味わって飲むか、ところてん、コンニャク、きのこ、トマトなどの低エネルギーの食品をとりましょう。
●外食、ファストフードに注意する
外食やファストフードは一般的にエネルギーが高く、脂肪、炭水化物が過剰で野菜が足りません。一部を食べ残し、サラダを追加するなどの工夫が必要です。食事はなるべく家でとるようにして、外食の回数を少なくするようにします。
●アルコール摂取に注意する
アルコールは高エネルギーで肥満や脂肪肝を助長するので、できれば避けます。また、自制心がゆるんで食欲が亢進する点でも注意が必要です。つまみには低エネルギーのものを選びます。
●ストレスを食べること以外で解消する
食べることでストレスを解消するのは、肥満の原因になることの多い生活習慣です。ストレスをためないようにし、趣味などの手段で解消するようにします。
●運動をする習慣をつける
運動不足と肥満の関係はよく知られた事実です。運動不足は肥満の原因であるとともに、肥満が原因で体を動かすのがおっくうにもなるという結果でもあり、悪循環を形成します。
現代人のライフスタイルはどうしても運動不足になりやすく、それによって太りやすい代謝状態になってしまいがちです。運動療法のところで述べたことを参考に、1日の決めた時間に自分でやりやすい運動をするようにします。日常生活のなかで、通勤の行き帰り、会社内の移動、仕事のための移動、買い物など、できるだけ歩く機会を増やす工夫も大切です。
●さまざまなダイエット法にとびつかない
ちまたには、さまざまなダイエット法の情報があふれています。正しいものもありますが、誤ったダイエット法も多いので気をつける必要があります。
たとえば、特定の食品(リンゴ、ヨーグルトなど)ばかり食べる方法がありますが、体に必要な栄養素が欠乏するため、貧血、肌荒れ、骨粗鬆症などの健康障害を起こしたり、体脂肪ではなく体の構成成分である蛋白質が減少したりします。
また、体重減少効果があるとして、さまざまな健康食品や民間薬が通信販売やインターネットで売買されています。基本的に怪しいものには手を出さないのが賢明です。死亡者の出た中国のやせ薬のように重い副作用を起こすこともあります。健康食品の安全性・有効性の情報は、独立行政法人国立健康・栄養研究所のホームページ(http://hfnet.nih.go.jp/)に最新情報を含めてまとめられていますので、参照するとよいでしょう。
これまでに述べてきたように、正しい知識のもとに食事療法・運動療法で徐々に体重を減らすのが、医学的にもすすめられる方法です。
 表14 100k
表14 100k
 表17 肥満とやせの判定表
表17 肥満とやせの判定表
 図12 上半身肥満と下半身肥満
図12 上半身肥満と下半身肥満
 図13 皮下脂肪型肥満(右)と内臓脂肪型肥満(左)
図13 皮下脂肪型肥満(右)と内臓脂肪型肥満(左)