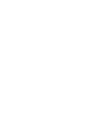 肝臓・胆嚢・膵臓の病気
肝臓・胆嚢・膵臓の病気
- 家庭の医学大全科
- 分類から調べる
- 肝臓・胆嚢・膵臓の病気
- 肝がん(肝細胞がん)
肝がん(肝細胞がん)
かんがん(かんさいぼうがん)
Hepatic cancer (Hepatocellular carcinoma)
初診に適した診療科目:消化器科 内科
分類:肝臓・胆嚢・膵臓の病気 > 肝臓の病気/肝がん
広告
広告
どんな病気か
肝がんには、肝臓そのものから発症した原発性肝がんと、他の臓器のがんが肝臓に転移した続発性肝がん(転移性肝がん)があります。原発性肝がんの約90%を肝細胞がんが占め、約10%が胆管細胞がんです。一般的に肝がんというと肝細胞がんを指しています。
日本では年間約3万1000人の肝がんによる死亡者がおり、男性では肺がん・胃がんに次いでがん死の第3位を占めています。2000年前後より肝がんの年間発症率は横ばいになりつつあり、肝がんで死亡する人はわずかに減少傾向にあります。
肝細胞がんは他臓器のがんと異なり、基礎疾患として慢性の肝臓病(慢性肝炎または肝硬変)のあることが多く、長期に“肝細胞の破壊・再生を繰り返すこと”が肝がん発がんの大きな原因と推定されています。B型肝炎ウイルスの保菌者では、ウイルスそのものが発がんを起こしうるとも考えられています。
原因は何か
日本では、肝細胞がん患者さんの多くがB型またはC型肝炎ウイルスに感染していて、一部の患者さんは大酒家です。このような“肝硬変を起こしうる原因”は、同時に“肝細胞がんを起こしうる遠因”となっています。
日本では、もともと肝障害がまったくない人に肝がんができることはまれです。ウイルス性慢性肝炎や肝硬変の患者さんでは、これらの病気が進行している人、高齢の人、男性などで、発がんの可能性が高い傾向があります。
症状の現れ方
腹部超音波、X線CT、MRIなどの検査で発見される直径5㎝以内の肝がんであれば、通常は無症状です。直径が5〜10㎝の肝がんになると、腹部が張った感じや腹痛などの症状を起こすこともあります。
肝がんが大きくなるに伴って、肝機能が低下することが多く、もともとある“肝硬変が悪化した症状”として、黄疸や腹水の増加などの症状が出ることもあります。小型であっても、肝がんが破裂を起こして腹腔に大出血を起こすと、腹部の激痛と血圧低下が起こり、一気に生命が危険な状態に陥ることもあります。
検査と診断
肝がんの診断は、腫瘍マーカーの測定(血液検査)と画像診断によって行われます。
一番有名な腫瘍マーカーであるAFP(アルファ胎児性蛋白)は、慢性肝炎や肝硬変だけでも高い数字を示すこともありますが、50〜100ng/ml以上の高値になると肝がんを疑う根拠になります。第二の腫瘍マーカーであるPIVKA‐Ⅱ(ピブカ・ツー)は3㎝以内の小型肝がんでは陽性になることが少ないのですが、陽性に出れば肝がん診断の特異性が高い(肝がん以外の病気であることが少ない)ことで有名です。
直径2〜3㎝の小型肝がんのうちに発見するためには、腹部超音波検査(図11)、CT(図12)、MRIなどの定期的な画像診断によるスクリーニング検査を続けることが必須です。肝がんは多くの場合、慢性の肝臓病がある人に現れるため、慢性肝炎や肝硬変の患者さんでは、年に数回の検査が行われます。
直径2㎝以下の肝がんのなかには、腫瘍の性格がおとなしい高分化型肝がんのことがあり、通常の画像診断では確定診断が困難なことがあります。この場合には、細径針腫瘍生検(細い針で組織を採取して顕微鏡で診断する)を行うこともあります。
治療の方法
肝細胞がんの治療法としては、①外科的肝切除、②経皮的エタノール局注療法(PEIまたはPEITと略)、③ラジオ波凝固療法(RFAと略)、④肝動脈化学塞栓療法、⑤放射線療法などがあります。最近では、これらの治療法が行えないような進行した肝がんに対して、分子標的薬といった内服治療により生存期間を延ばすことができることも知られています。
肝がんは直径2〜3㎝の大きさになると、門脈を経由して肝内各所に転移を始めます(肝内転移多発)。一方、肝細胞がんは基礎疾患として慢性肝疾患、とりわけ肝硬変があることが多く、いったん根治的に切除しても、新規の発がんを起こして再発することも少なくありません(多中心性多発)。
実際の患者さんでは、この2つの多発のパターンをはっきり区別することは必ずしも簡単ではありませんが、前者の肝内転移多発のほうががんとしての性質が強く、生存率に及ぼす影響が大きいといえます。
肝がんでは、この①多発性(1個か複数か)、②腫瘍の大きさ、③肝機能の重症度の3点を考慮してそれに適した治療法が選択されることが多く、さらに、④がんの存在部位(肝臓の表面か深部か)を考慮することもあります。
代表的な治療法の長所・短所を表14にまとめました。肝がんに対して行われるさまざまな治療法は、“根治性”“多中心性発がんの起こりやすさ”“肝予備能”など、すべての観点を考慮して決定するもので、ただひとつの治療法が最も優れているということはありません。
さまざまな治療法を柔軟に組み合わせて行うこと(集学的治療)こそが、肝がん患者さんの生活の質(QOL)を保ち、長期の生存につながるといえます。
病気に気づいたらどうする
肝がんの症状は、基礎にある慢性肝炎や肝硬変の症状と非常に似ているため、肝がんであるという特有な症状、サインはほとんどありません。すなわち、腹水、むくみ、黄疸などの症状があっても、これが肝がんの症状であるかどうかの区別は困難です。
急速に悪化する腹部膨満感(張り感)では、急激に増大しつつある肝細胞がんの可能性があります。また、強い腹痛は肝がんの腹腔内破裂(出血)の可能性があり、緊急にその状態を調べる必要があります。
ALT(GPT)値の異常などの肝障害があったり、B型肝炎・C型肝炎ウイルスが陽性であれば、医師に対して腹部超音波検査を受けることを希望し、早い時期に肝臓内部のチェックをしてください。そして、基礎に肝臓病があって、腹部超音波やCTで肝臓内部に腫瘤(しこり、影)が見られたら、ただちに肝臓の専門医の診察を受けてください。良性腫瘍のこともありますが、自覚症状の出てこない早期に肝細胞がんを診断することが、十分な治療を行うためにはどうしても必要です。
受診する科目は、消化器科または内科です。病気の性格からは、肝がんと診断される前の段階(慢性肝炎、肝硬変)から、定期的に肝臓病の専門医に受診していることが大切です。こうすれば早期発見・早期治療の可能性が高くなります。
生活面での注意は、背景の肝臓病の程度により禁酒、安静、食事制限などが要求される場合がありますが、一般にはこれ以上に特別なものはありません。
 図11 肝細胞がん(腹部超音波像)
図11 肝細胞がん(腹部超音波像)
 図12 肝細胞がん(X線CT像)
図12 肝細胞がん(X線CT像)
 表14 肝細胞がん治療法の長所と短所
表14 肝細胞がん治療法の長所と短所