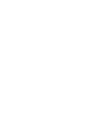 肝臓・胆嚢・膵臓の病気
肝臓・胆嚢・膵臓の病気
- 家庭の医学大全科
- 分類から調べる
- 肝臓・胆嚢・膵臓の病気
- 原発性胆汁性肝硬変
原発性胆汁性肝硬変
げんぱつせいたんじゅうせいかんこうへん
Primary biliary cirrhosis
初診に適した診療科目:消化器科 内科
分類:肝臓・胆嚢・膵臓の病気 > 肝臓の病気/肝硬変・門脈圧亢進症
広告
広告
どんな病気か
肝臓には肝細胞でつくられた胆汁が排泄される管、すなわち胆管系があります。これは、肝小葉内の隣接する肝細胞により形成される毛細胆管に始まり、細胆管をへて門脈域にある小葉間胆管に続いています。さらに、これが集合して太い隔壁胆管になって肝管に連続しています。肝門部で左右の肝管が合流して総肝管となり、肝外胆管に移行して総胆管へとつながっていきます。
原発性胆汁性肝硬変(PBC)は、中年の女性に発生することが多い特徴的な病気です。肝臓のなかの小葉間胆管から隔壁胆管にかけての部位が、自己免疫の機序(メカニズム)によって徐々に破壊されるために胆汁の流れが悪くなり、その結果「慢性肝内胆汁うっ滞(慢性非化膿性破壊性胆管炎)」が起こり、最終的には肝硬変へと進行する病気です。
したがって、原発性胆汁性肝硬変という病名は病気の最終段階の病態を示したもので、最初から肝硬変で始まるというわけではありません。事実、ほとんどは肝硬変になる前に診断されているので、原発性胆汁性肝硬変と診断されても肝硬変になっていない人が大部分です。
日本では、旧厚生省「難治性の肝炎」の調査研究班(1992年)により、表9に示すような診断基準が定められています。
原因は何か
この病気の胆管破壊には、胆管上皮細胞を標的とした自己免疫反応が関係していると考えられていますが、その発症機序が完全に解明されているわけではありません。しかし、各種自己抗体が陽性で、しばしば他臓器の自己免疫性疾患(たとえば、シェーグレン症候群、慢性甲状腺炎、関節リウマチなど)を合併するなど、自己免疫性疾患(膠原病)としての特徴をもっています。
最近、小葉間胆管もしくは隔壁胆管における主要組織適合性複合体(MHCクラスⅠ、Ⅱ抗原)の異常な表出と細胞障害性T細胞の作用、抗ミトコンドリア抗体の対応抗原のひとつであるピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体(PDC)のE2成分(PDC‐E2)の胆管上皮への表出とこれを標的とした免疫反応など、胆管破壊に関係する自己免疫性反応が報告されています。
原発性胆汁性肝硬変は、母娘、姉妹での発症例の報告があることから、その発症に何らかの遺伝的要因の関与も推定されています。
症状の現れ方
慢性の肝内胆汁うっ滞の結果として、初発症状としては皮膚のかゆみが最も多く、黄疸がこれに続きます。このような症状がみられる場合を「症候性原発性胆汁性肝硬変」と呼びます。黄疸がいったん現れると、消えることはなく少しづつ増えることが多いようです。そのほか、脂質異常症(高脂血症)に由来する皮膚の黄色腫(もしくは黄色板)、肝腫大、カルシウムとビタミンDの吸収障害による骨粗鬆症などを伴います。
また、門脈圧亢進症状が高頻度に現れるため、食道静脈瘤とその破裂による出血もみられます。少数ですが、肝硬変になる前から門脈圧亢進が先行して、食道静脈瘤や脾腫による血小板減少を伴って、最初に食道静脈瘤で発見されたり、また、その破裂による消化管出血を初発症状とする患者さんがいます。
長期の胆汁うっ滞が続くと、最終的には胆汁性肝硬変となり、高度の黄疸、腹水、浮腫、出血傾向、門脈圧亢進に関連する脾腫、血小板減少症など、通常の肝硬変の肝不全時にみられる症状が現れるようになります。
一方、皮膚のかゆみや黄疸などの症状が認められない場合は「無症候性原発性胆汁性肝硬変」とされます。
最近では、新たに診断される人のほぼ3分の2は無症候性であり、その多くは検診あるいは他の病気の治療中に偶然発見されています。無症候性と診断された人の多くは症状が出ないまま経過することが知られていますが、どの患者さんがやがて進行して症候性になるのか、また無症候性のまま経過するのかは臨床的に判別することはできません。
検査と診断
肝内の初発病変は、小葉間胆管あるいは隔壁胆管などの中等大の胆管にあり、その部位の炎症性変化により胆管が破壊されるために、胆汁の流出が阻害され、それに伴って胆汁成分が血中で増加します。
一般的な血液検査での特徴は、赤沈の亢進、アルカリホスファターゼ(ALP)、γ‐GTP、およびLAPなどのいわゆる胆道系酵素の血中レベルの上昇で、そのほか、高コレステロール血症、血清銅値の上昇がみられます。胆汁の流れが悪くなるために、ビタミンA、D、E、Kなどの脂溶性ビタミンの吸収も悪くなるので、骨粗鬆症が悪化する原因になります。
AST(GOT)、ALT(GPT)などの肝細胞障害を反映する検査項目は、病気の初期には上昇がみられないか、もしくは軽度上昇にとどまります。しかし、胆汁うっ滞が強くなって肝細胞障害が現れるとALT、AST値も上昇します。
最も特徴的な検査所見は、IgMの上昇、抗ミトコンドリア抗体陽性、抗ミトコンドリア抗体亜分画の抗M2抗体陽性などです。
確定診断は、腹腔鏡下もしくは超音波下で肝生検を行って、この病気に特徴的な「慢性非化膿性破壊性胆管炎」の病理組織学的所見を確認することです。
区別すべき疾患として、慢性肝内胆汁うっ滞症の共通した臨床像を示す薬剤起因性肝内胆汁うっ滞、肝内型原発性硬化性胆肝炎、成人性胆管減少症、閉塞性黄疸などがありますが、いずれの病気も抗ミトコンドリア抗体が陰性です。
治療の方法
①日常生活と食事
診断が確定したあとは、定期的な検査を行って経過観察をする必要があります。無症候性の場合はもちろん、症候性であっても、症状が比較的落ち着いていたり、ウルソデオキシコール酸(UDCA:ウルソ)などの服用で経過が良好な場合も、同薬剤の服用を続けながら普通の日常生活が可能です。
食事は銅含有量の多い食品(貝類、レバー、キノコ類、チョコレートなど)を避け、胆汁分泌が不良であることを考慮して、脂肪をとりすぎないように注意します。とくに黄色腫や高コレステロール血症が明らかな場合には、高脂血症に準じた食事療法が大切です。
骨粗鬆症は中年以降の女性では注意が必要なので、カルシウム、リン、亜鉛などのミネラルの摂取と適度な運動による骨塩量の減少予防対策が重要です。
②薬物療法(表10)
確立した治療法はありませんが、そのなかで有用性が認められているのはウルソデオキシコール酸(ウルソ)と肝移植療法です。そのほか、対症的に、高脂血症にベザフィブラート(ベザトールSR)の内服を、皮膚のかゆみにコレスチミド(コレバイン)や抗ヒスタミン薬(ポララミン、ジルテックなど)の内服を、そしてビタミン吸収障害に脂溶性ビタミン製剤(A、D、K)の注射などで、それぞれ投与します。
コルチコステロイド(副腎皮質ホルモン薬)は、初期の原発性胆汁性肝硬変や自己免疫性肝炎を合併している場合に適応されますが、長期に服用すると骨粗鬆症を悪化させます。眼の乾燥、口腔乾燥などのシェーグレン症候群に対しては、対症的に人工涙液・唾液などを用います。
原発性胆汁性肝硬変に対するUDCA療法では、治癒するという報告はありませんが、血液生化学検査ではALP、γ‐GTP、総ビリルビン、トランスアミナーゼなどが改善するとされています。アルブミンや凝固能は変わりません。また、皮膚のかゆみや全身倦怠感などの自覚症状は変わらないという報告が多くみられます。最も重要な肝生検組織像や生存率に及ぼす影響については、一致した見解はありません。
UDCA療法が普及して十数年が経過して、この病気の生存率は改善されてきたような印象を受けます。しかし、実際には経過がゆっくりであり、また患者さんによって進行がさまざまなので、肝組織や生存率の改善の効果判定には、多数の患者さんについてより長期に観察する必要があると思われます。
最近、高脂血症治療薬のベザフィブラートには、胆汁うっ滞による胆管障害とそれに伴う炎症の改善、免疫調整作用など多様な効果があることが明らかにされています。ベザフィブラート単独、もしくはUDCAとの併用療法が肝内胆汁うっ滞の改善に有効との報告があります。
③肝移植
原発性胆汁性肝硬変は肝移植のよい適応疾患です。日本では、欧米と異なって脳死肝移植はまだ少数で、生体部分肝移植が行われることが多くなっています。
米国のピッツバーグ大学における脳死肝移植の成績では、原発性胆汁性肝硬変を含む胆汁うっ滞性肝硬変は、適切な移植時期を選択することで移植後の5年生存率は70%を超えています。移植時期を決定するための予後予測モデルが開発されていますが、病期の進んだ患者さんでは移植後の生存率は低くなっています。
 表9 原発性胆汁性肝硬変(PBC)診断基準(主要項目)
表9 原発性胆汁性肝硬変(PBC)診断基準(主要項目)
 表10 原発性胆汁性肝硬変での薬剤処方例
表10 原発性胆汁性肝硬変での薬剤処方例