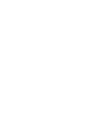 肝臓・胆嚢・膵臓の病気
肝臓・胆嚢・膵臓の病気
肝硬変
かんこうへん
Liver cirrhosis
初診に適した診療科目:消化器科 内科
分類:肝臓・胆嚢・膵臓の病気 > 肝臓の病気/肝硬変・門脈圧亢進症
広告
広告
どんな病気か
肝硬変は、ひとつの独立した疾患というよりも、種々の原因によって生じた慢性肝炎が治癒しないで、長い経過をたどったあとの終末像であって、その肝病変は一般に非可逆的(元にはもどらない)と考えられてきました。すなわち肝硬変とは、種々の原因によってびまん性の肝細胞の壊死と炎症、再生が繰り返し起こり、その場所に高度の線維が増生した結果、肝臓の本来の小葉構造と血管系が破壊されて偽小葉と再生結節が形成され、肝臓が小さく、かつ硬くなる病気です(図6)。
したがって臨床的には、肝細胞障害による肝機能の低下、門脈圧亢進、および門脈‐大循環系短絡(シャント)形成の3大要因により、症状の乏しい初期から多様な症状を示す進行期まで、その程度はさまざまです。肝硬変は肝臓だけの病気ではなく、全身性疾患だという認識が大切です。
原因は何か
肝硬変の原因としては、①ウイルス性、②アルコール性、③自己免疫性、④薬剤・毒物性、⑤胆汁うっ滞性、⑥うっ血性、⑦栄養・代謝障害性、⑧感染症(寄生虫を含む)など、多岐にわたることが知られています(表4)。日本の肝硬変では肝炎ウイルス(C型、B型)によるものが最も多く、次いでアルコールによるものの順になっています。ウイルス性肝硬変では、C型肝炎ウイルス(HCV)によるものが大半を占めています。
1994年の日本大学の調査では、肝硬変537例中、C型が60・6%、B型が9・5%、アルコール性が16・7%、非B非C型が8・2%、特殊型が3・3%の頻度となっています(図7)。
症状の現れ方
肝硬変にみられる臨床症状と検査所見の由来を表5に示します。肝硬変の症状の主なものは、肝細胞の機能障害と門脈圧亢進により生じます。
代償性肝硬変(後述)では、自覚症状をほとんど訴えないことが多く、あっても軽微です。一部には、まったく自覚症状もなく、かつ通常の血液生化学検査でも異常を示さず、偶然の機会に発見される、いわゆる潜在性肝硬変と考えられる患者さんもいます。
肝機能障害が進行するとともに、肝臓の予備能力が低下してくると非代償性肝硬変(後述)になります。こうなると全身倦怠感、脱力感、易疲労感、尿の色が濃く染まる、腹部膨満感、吐き気(悪心)、嘔吐、腹痛など、消化器症状を主とする全身症状を訴えることが多くなります。しかし、これらは必ずしも肝硬変に特徴的なものではありません。
さらに重症になると、黄疸、腹水、吐血、肝性昏睡など、続発症・合併症に伴う症状が現れるようになります。また、肝硬変の皮膚所見としては、黄疸のほかに、くも状血管腫、女性化乳房、手掌紅斑、皮膚の色素沈着、出血傾向、皮下出血、太鼓ばち状指、白色爪などが認められることが多く、診断上役に立ちます。
検査と診断
肝硬変は、本来、病理組織学的な概念ですが、すべての患者さんに腹腔鏡検査や肝生検を繰り返し行って、顕微鏡検査で病理組織診断を確定することは容易ではありません。肝硬変に対する特異的な検査法はありませんが、通常は血液生化学的検査、血液学的検査、画像検査などから得られた情報を総合的に判断して診断します。
肝硬変は、臨床的な機能分類として、肝硬変の原因を問わず、肝不全症状の有無から代償性(期)と非代償性(期)とに分けられます。
代償性肝硬変とは、黄疸、腹水、浮腫、肝性脳症、消化管出血などの肝機能低下と門脈圧亢進に基づく明らかな症候のいずれも認められない病態です。非代償性肝硬変とは、これらの症候のうちひとつ以上が認められる病態です。
肝臓は脂質、炭水化物、蛋白質、アミノ酸の代謝およびエネルギー代謝など栄養代謝の中心的な臓器ですので、肝硬変、とくに機能不全を来す非代償性肝硬変では、さまざまな栄養代謝障害が引き起こされます。
通常、肝硬変の診断では、肝細胞の機能障害を反映したアルブミン、コリンエステラーゼ、凝固因子(プロトロンビン時間、ヘパプラスチン)、コレステロールなどの低下、血漿遊離アミノ酸異常、間葉系反応を反映したγ‐グロブリンの上昇、硫酸亜鉛混濁試験・チモール混濁試験(膠質反応)などの高値、肝線維化マーカーの上昇、肝循環動態の異常を反映したインドシアニングリーン負荷試験(停滞率、最大除去率)の上昇、そして門脈亢進に伴う脾機能亢進を反映した血小板数の減少などが重要です。
新犬山分類による慢性肝炎と肝硬変の病期と血小板数(基準値:14〜45万/μl)の関係では、病期の進行とともに段階的に血小板数は減少していき、血小板数が12万/μl以下に低下してくると肝硬変へ進展する可能性が高くなります。
肝硬変の治療方針を決定したり生活指導を行う場合には、病態の重症度判定が非常に重要です。肝硬変の重症度および手術適応決定の際にはチャイルド分類が用いられます(表6)。
肝機能検査と予後との関係では、ビリルビン、アルブミン、凝固因子、γ‐グロブリン、ALP、コリンエステラーゼ、総コレステロール、総胆汁酸、75g糖負荷試験、インドシアニングリーン負荷試験(最大除去率)などが重要です。
血清アルブミン量に注意
血清アルブミン量と肝硬変の経過・予後には密接な関係があります。肝硬変の患者さんでは、蛋白質・エネルギー低栄養状態が約70%に認められます。このような病態は、免疫機能や生体防御機能の低下、易感染性、病気の回復や創傷の治癒の遅れ、精神機能の低下などをまねき、腹水・浮腫の原因になったり、日常生活動作(ADL)や生活の質(QOL)の低下へとつながります。
このような障害を栄養学的に予防するには、代償性と考えられる肝硬変であっても、食事摂取が十分にもかかわらず血清アルブミンが3・5g/dl以下、BTR(分岐鎖アミノ酸/チロシン比)が3・5以下、フィッシャー比が1・8以下になれば、分岐鎖アミノ酸顆粒(BCAA顆粒、商品名リーバクト)を投与して、早期に低アルブミン血症の改善を図ることが望まれます。
しかし、重症度が進行した場合(チャイルド分類のグレードC)は十分な効果が得られないことが多いため、軽度もしくは中等度(グレードAもしくはB)のうちに早めに投与を開始したほうがよいと思います。
黄疸の経過とビリルビン値
通常、肝硬変の黄疸は軽度で、血清ビリルビン値も多くは2〜3㎎/dl以下です。しかし、黄疸が消退せず、また漸増して眼球結膜と皮膚の明らかな黄染を示す場合は、肝細胞障害を伴う肝不全の病態を示し、予後不良の徴候となります。
肝硬変の病態が重症になるにつれて、抱合ビリルビン/総ビリルビン比は低下し、逆に抱合されない間接型ビリルビンの占める割合が大きくなる症例が増えます。これは肝予備能が次第に低下して、ビリルビン代謝が破綻しつつ(あるいは破綻して)血清ビリルビン値が増加していることを示しています。
肝硬変の経過・予後を占ううえで、黄疸は血清アルブミン値と腹水の存在に次いで有用な指標となりますが、通常はチャイルド分類による判定が有用です。
合併する肝がんの早期診断
肝硬変の3大死亡原因は、肝がん、肝不全、食道静脈瘤の破裂に伴う消化管出血です。最近は肝がんの占める割合が70%と高くなり、次いで肝不全が20%、消化管出血が5%の順です。この背景には、栄養療法の進歩、食道静脈瘤に対する内視鏡的治療の向上、抗生剤と利尿薬の開発・導入、アルブミン製剤の繁用などによる消化管出血死や感染死の減少があります。
肝硬変の患者さんの生存率が高まることは、必然的に患者さんの高齢化を来し、同時に肝がん発生率の増加につながってくることを意味します。肝がんの予測は、いかなる場合でも常に念頭におく必要があります。
肝細胞がんの背景病変をみると、その80%に肝硬変が認められており、一部が進んだ慢性肝炎です。したがって、進んだ慢性肝炎と肝硬変は前がん病変であり、肝細胞がんの超高危険群といえます。
肝硬変での肝細胞がんの推定発がん率は、年6〜7%です。早期の肝細胞がんを見過ごさないために、超高危険群ならびに高危険群の患者さんは、その危険度に応じて一般肝機能検査といっしょに2〜3カ月に1回の腫瘍マーカー(AFP、PIVKA‐Ⅱ、AFP‐L3分画)の測定、3〜6カ月に1回の超音波検査、6カ月に1回程度の腹部CT検査を受けることが望まれます。
治療の方法
肝硬変の治療は、その病態が代償性か、非代償性かによって異なりますが、現在の病態をさらに悪化させることなく生活の質(QOL)と日常生活動作(ADL)を維持、改善させ、予測される合併症に早期に対応していくことが重要です(表7)。
●生活指導
過労を避け、禁酒し、バランスのよい食事をとり、規則正しい生活をするよう生活指導を受けます。しかし、病態が急性増悪して、自覚症状と肝機能障害が強くなったり、あるいは黄疸、浮腫・腹水、意識障害などが現れているような時期には入院管理が必要になります。
●一般的な薬物療法
肝硬変そのものに対する治療薬はありません。肝障害の重症度に応じて、肝臓加水分解物(プロヘパール)、肝臓抽出薬(アデラビン9号)、胆汁酸製剤(ウルソデオキシコール酸:ウルソ)、グリチルリチン製剤(内服薬がグリチロン、注射薬が強力ネオミノファーゲンC)、漢方薬、ビタミン剤などを単剤、またはいくつかの薬剤を組み合わせて多剤服用、もしくは静脈注射を併用します。
これらの肝臓用薬(肝庇護薬)の服用・静脈注射によって、肝細胞の壊死・炎症を鎮静化させてAST(GOT)、ALT(GPT)を基準値の2倍以内のできるだけ低い値に維持できると、肝がんの合併を抑制して、発がんの時期を遅らせることができます。
非代償性の肝硬変では、黄疸、浮腫・腹水、肝性脳症などへの対症的な治療対策がそれぞれ必要になります。原則的には、安静臥床、食塩制限(1日3〜6g)、軽度の水分制限、蛋白質の摂取制限(1日40g程度)が行われます。そのうえで、浮腫・腹水には利尿薬を投与します。
もしも低アルブミン血症が高度のために、利尿薬の投与にもかかわらず浮腫・腹水が改善しない場合には、アルブミン製剤を補給し、血清アルブミン濃度が3g/dl以上になるようにします。
なお、いろいろな内科的治療により軽減できない中等量以上の腹水(難治性腹水)に対しては、腹腔頸静脈シャント(LeVeenシャント等)術、腹水濾過濃縮再静注法、経頸静脈肝内門脈大循環シャント術などが行われることもあります。
●ウイルス性肝硬変での抗ウイルス療法
C型肝硬変のうち、腹水、肝性脳症および門脈圧亢進などの既往がない代償性肝硬変では、インターフェロン(IFN‐α、IFN‐β)が適応となります。また、代償性・非代償性B型肝硬変では、核酸アナログ製剤(エンテカビル、ラミブジン、アデホビル)が適応となります。
平成20年度厚生労働科学研究で提言された「ウイルス性肝硬変に対する包括的治療のガイドライン」に示すように、ウイルスの駆除・減少によりAST(GOT)・ALT(GPT)値の正常化を目指し、肝組織学的な改善が認められることから、肝細胞がんの発生リスクを低くすることが期待できます(表8)。非代償性肝硬変では、代償性肝硬変への改善を目標とし、ひいては肝発がん予防を目指す治療となります。
なお、C型肝硬変に対するインターフェロン治療は、慢性肝炎より著効率が低く、また副作用の発生率や治療脱落率などが高く、費用対効果が悪いという問題点があります。しかし著効が得られれば、予後は改善されます。
●肝性脳症の治療
肝性脳症は肝疾患に伴う精神神経症状のことで、意識障害が昏睡に進行した場合を肝性昏睡といいます。そのほか、性格変化や知能低下などがみられます。
肝性脳症の治療は、あらかじめ脳症の合併が予想される患者さんでは、予防的処置(高アンモニア血症の誘因の回避、特殊組成アミノ酸製剤の服用など)を普段から行っておくことが大切です。
脳症が発症した時には、脳症から覚醒させるための積極的な治療が行われます。すなわち、高アンモニア血症対策が中心になりますが、誘因(高蛋白食、便秘、消化管出血、低カリウム血症に伴うアルカローシス、向精神薬など)を除去したうえで、便秘の回避(浣腸、下剤)、非吸収性の抗生剤(フラジオマイシン、ポリミキシンB、バンコマイシンなど)、合成二糖類(ラクツロース、ラクチトール)の経口投与もしくは浣腸、さらに分岐鎖アミノ酸(BCAA)を主体とした特殊組成アミノ酸製剤(輸液または内服)などで、総合的に治療します。
●肝移植
2004年に肝移植対象疾患の保険適応が拡大されたことにより、B型およびC型肝硬変や肝がんに対する肝移植が増加しています。日本での肝硬変における肝移植適応は、末期肝不全状態を示す例となっており、一般的にはMELDスコアによって判定されます(15以上)。
その大部分は生体部分肝移植であり、脳死移植は極めて少ないのが実情です。肝移植による成績では、B型よりもC型肝硬変で予後が不良であり、移植後の抗ウイルス療法の確立が課題です。
●合併症への対処
肝硬変の合併症としては、食道静脈瘤と肝がんが重要です。食道静脈瘤では、静脈瘤破裂を予防する処置として、一般的には内視鏡的硬化療法(EIS)や静脈瘤結紮術(EVL)が行われます。外科的治療法としては、食道離断術とハッサブ手術があります。さらに最近は、頸静脈から経皮的にステントという器具を挿入し、門脈肝静脈短絡を形成する手術が行われています。
肝がんの合併に際しては、早期発見・早期治療が最も重要ですが、肝臓の予備能力の程度と肝内の腫瘍の占拠状況によって治療法の選択が異なってきます。
現在、肝がんの治療法としては、外科的肝切除術、経肝動脈塞栓術(TAE)、肝腫瘍内エタノール局注療法(PEIT)、ラジオ波焼灼療法(RFA)、経皮的マイクロ波凝固療法(PMCT)、リザーバー留置による抗がん薬動注化学療法、などが行われます。
進行肝がんに対しては、フルオロウラシル(5‐FU)の肝動注療法とインターフェロンの全身投与を併用することで、良好な成績が得られています。
* * *
以上、肝硬変の診療では、原因の確定、病態の重症度の評価と予後の予測、栄養評価とその対策、肝がんをはじめとする種々の合併症を視野に入れた適正な診断と治療対策、そして患者さんのADLとQOLの改善と長期維持を考慮した生活指導などが大切になります。
肝硬変については、診断技術の進歩や管理方法の向上ばかりでなく、合併症に対する治療についても著しく進歩してきました。したがって、肝硬変を慢性肝疾患の終末病態としてとらえるのは適切ではなくなってきています。
 図6 肝硬変(腹腔鏡像)
図6 肝硬変(腹腔鏡像)
 表4 肝硬変の病因的分類
表4 肝硬変の病因的分類
 図7 肝硬変の成因別頻度の推移
図7 肝硬変の成因別頻度の推移
 表5 肝硬変にみられる臨床症状、検査所見の由来
表5 肝硬変にみられる臨床症状、検査所見の由来
 表6 チャイルド分類を用いた肝予備能の評価
表6 チャイルド分類を用いた肝予備能の評価
 表7 肝硬変治療の指針
表7 肝硬変治療の指針
 表8 ウイルス性肝硬変に対する包括的治療のガイドライン
表8 ウイルス性肝硬変に対する包括的治療のガイドライン