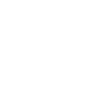 食道・胃・腸の病気
食道・胃・腸の病気
胃がん
いがん
Gastric cancer
初診に適した診療科目:消化器科 内科 外科
分類:食道・胃・腸の病気 > 胃・十二指腸の病気
広告
広告
どんな病気か
胃がんは、胃の悪性新生物の95%を占める上皮性(粘膜由来)の悪性腫瘍で、日本では肺がんに次いで死亡率の高いがんです。男女比は2対1と男性に多く、男女とも60代に発症のピークがあります。
がんの深達度(深さ:漿膜側への広がり)により早期がんと進行がんに分類されますが、早期胃がんは大きさやリンパ節への転移の有無に関係なく、深達度が粘膜内または粘膜下層までにとどまるものと定義されています。日本は、世界的にみても早期発見の技術や手術成績が優れており、近年の有効な抗がん薬の開発も相まって胃がんの治癒率は明らかに改善しています。決して、進行がん=末期がんではありません。
原因は何か
胃がんの発生には、環境因子の影響が強いと考えられています。
最近になって、ヘリコバクター・ピロリ(Hp:ピロリ菌)と呼ばれる細菌が胃のなかにすみ着いて胃がんの原因になっていることがわかってきました。この細菌は、1994年に国際がん研究機関によって“確実な発がん因子”と分類されました。菌によって慢性の炎症が起こり、慢性萎縮性胃炎をへて腸上皮化生と呼ばれる状態になり、これらが胃がんの発生母地になると考えられています。
この菌は、50歳以上の日本人の約8割が保菌しています。Hp 陽性の患者さんで粘膜の萎縮の強い人は、萎縮のない人に比べて5倍も胃がんになりやすく、またHp 陽性の患者さんで腸上皮化生のみられる人は、みられない人に比べて6倍も胃がんになりやすいとされています。ただし、Hp 陽性者が胃がんに移行する確率は0・4%と低く、ヒトではHp 感染だけでは胃がんにはならず、Hp によって萎縮性胃炎が進行したところにさまざまな発がん因子が積み重なり、胃がんが発生すると考えられています。
分子レベルでは、この過程でがんをつくる方向にはたらく遺伝子(がん遺伝子)の活性化や、がんを抑える遺伝子(がん抑制遺伝子)の不活性化が起こっています。
一方で、胃がんの発生は食生活に関係があるといわれています。たばこ、高塩分食、魚や肉などの焦げは発がん促進因子とされており、逆に緑黄色野菜に含まれるビタミンA、C、カロチンは発がん抑制因子とされています。
胃がんと胃潰瘍はまったく別のものと考えられており、同じHp 感染が原因でありながら十二指腸潰瘍の患者さんには胃がんができないことも知られています。また、胃ポリープの一部(腺腫性ポリープ)は前がん病変と考えられていますが、がん化率はそれほど高いものではありません。
症状の現れ方
胃がんに特有な自覚症状はありません。早期胃がんの多くは無症状で、一般には上腹部痛、腹部膨満感、食欲不振を契機に、X線造影検査や内視鏡検査で偶然に発見されます。
進行がんになると体重の減少や消化管の出血(下血や吐血)などがみられ、触診で、上腹部にでこぼこの硬い腫瘤を触れることもあります。腹水がたまったり、体表にリンパ節が触れるような場合は、がんが全身に広がったことを示し、このような場合は手術の対象にはなりません。
検査と診断
バリウムによる胃の二重造影法は日本で開発され、胃がんの診断学の確立に大きな貢献をしてきました。しかしながら、現在は電子スコープの普及と内視鏡の細径化が進み、組織の採取が可能な内視鏡検査が主流になっています。
良性・悪性の最終診断は内視鏡下に組織を採取し(生検)、病理医による組織診断により決定されます。胃がんは病理学的には、大部分が正常の胃粘膜構造に似た分化型腺がんに分類されます。ただし、病理診断は良性・悪性の質的な診断であり、これだけでは病期(がんの進行度)を決定することはできません。
胃がんにかかわらず、がんの治療方法は後述するように病期によって決まります。病期はがんの深達度と広がりの程度によってⅠ期からⅣ期に大きく分類され、深達度とリンパ節への転移に応じてⅠ期はⅠAとⅠBに、Ⅲ期はⅢAとⅢBに亜分類されます(表3)。がんの深達度を評価するためには、内視鏡の肉眼所見に加えて超音波内視鏡が有用で、胃外への病気の広がり(リンパ節転移、他臓器転移の有無)を知るためにCTを行います。
いわゆる腫瘍マーカーは、胃がんではCEAやCA19‐9などが使われますが、全例で陽性になるわけではなく、また早期診断には無効であり、主に再発予測など進行がんの術後の経過観察に用いられます。現在のところ、早期がんのスクリーニングに有用なマーカーはありません。
治療の方法
2004年に、日本胃癌学会が病期に応じた標準治療のガイドライン(第2版)をまとめて、広く一般にも公開しています(表3)。とくに、ⅠA期に対する内視鏡的粘膜切除術は患者さんへの肉体的負担が少ないこと、胃の機能が温存できること、また入院期間も短いことから日本では積極的に行われています。
最近では、ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術、コラム)という方法も広く行われるようになり、大きい病変をひとかたまりで切除することができる時代となりました。
手術不能な胃がんに対する抗がん薬治療は、いくつかのベストサポーティブケア(BSC:抗がん薬を使用しない対症療法)との比較試験の結果、明らかな延命効果が証明されています(生存期間中央値がBSCの3〜4カ月に対し、抗がん薬治療が10カ月)。しかし、具体的な薬剤の選択や投与法に関しては、いまだ研究段階にあり、経験豊富な施設、医師のもとでの治療がすすめられます。
また、セカンドオピニオンを積極的に聞くことも大切です。主に手術不能症例に対して、いろいろな代替医療(民間療法)が普及していますが、その多くは科学的根拠に乏しいものであり、これらの治療は十分な説明を受け、納得したうえで受けるようにしてください。
胃がん全体の5年生存率は、1963〜1969年の統計では44%でしたが、1979〜1990年の統計では72%と明らかに改善しています(国立がんセンター)。病期別の5年生存率はⅠ期92%、Ⅱ期77%、Ⅲ期46%、Ⅳ期8%(がん研究振興財団編「がんの統計1999」)となっています。
治療法の進歩にもかかわらず、治癒切除例の5年生存率が88%、非治癒切除例の5年生存率が11%であるのに対し、切除不能例の5年生存率は2〜3%と不良で完治は困難です(国立がんセンター)。内視鏡的切除例の5年生存率は、対象がⅠA期に限られていることもあり、80〜95%と外科切除と同等に良好です。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍に対してはHp の除菌療法が標準治療となっていますが、Hp の除菌によって胃がんの発生が抑えられるかどうかについては、現在、精力的に研究が進められています。ポジティブな結果が待たれますが、明確な答が出るには時間がかかりそうです。
病気に気づいたらどうする
体重の減少や消化管の出血が認められた場合はすぐに近くの消化器専門医を受診し、医師の判断に従って検査を受けてください。初診は外科でも内科でもかまいません。何らかの上腹部症状が続く場合は、内視鏡検査を受けることがすすめられます。胃がんによる上腹部の症状は潰瘍の場合とは違い、食事とは無関係に起こります。
無症状の場合でも40歳を超えたら、内視鏡もしくはX線検査による健康診断を定期的に行うことが早期発見につながります。自覚症状がなく早期に発見された人の5年生存率は97%であり、今や胃がんは早く見つければほぼ完全に治せる病気になっています。前述したように胃がんは食生活の改善により予防できる余地があり、バランスの取れた食生活を心がけることが大切です。
内視鏡的粘膜切除術(EMR)および内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)
1980年代に登場した内視鏡的粘膜切除術(EMR)は、診断のための切除から根治のための切除へと、内視鏡治療の分野に大きな変革をもたらしました(図24)。より安全で簡便なさまざまなEMR手技が次々と報告されるようになり、当初は1㎝以下の小さな病変のみが対象でしたが、徐々に大きな病変に対しても施行されるようになってきました。しかし、技術的な限界から1㎝を超える病変を確実に一括切除することは困難で、分割切除が許容されていました。ところが、分割切除後に約12%の局所再発があることがわかってきました。
1998年に、IT(絶縁チップ)ナイフを用いた内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が臨床応用され、一括切除率が飛躍的に向上したことから、早期胃がんの約半分は内視鏡での切除(=根治)が可能となりました。2006年4月の診療報酬改定によって、「胃の早期悪性腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術」が保険適応になり、ESDが社会的にも認知されるようになりました。
内視鏡的切除は、リンパ節郭清が不可能であるため、根治できる病変はリンパ節転移がないことが外科手術と大きく異なるところです。しかし、残念ながら、術前に早期胃がんのリンパ節転移の有無を正確に評価することはできません。
臨床においては、切除後に深達度(がんの深さ)や脈管侵襲(リンパ管や静脈へのがんの浸潤)の有無など、リンパ節転移に関係している因子を病理組織学的に評価することによって、「リンパ節転移の可能性が極めて低いがん」=「リンパ節郭清の必要がない局所切除で根治可能ながん」であることを確認しなくてはなりません。根治という観点から、“切除ができる”と“根治できる”を明確に理解したうえで治療方法を決定する必要があります。
ESDを行うにあたって、術中の偶発症(穿孔・出血)の頻度はEMRと比較すると高率で、知識と対策も含めた内視鏡技術の習得が不可欠となります。ESDは技術的な煩雑さから完成された手技とはいいがたく、今後もより安全・簡便な手技への進化が望まれる技術です。
内視鏡的切除といえども、最終目標は根治であることを念頭に置いた術前検査と治療方針の決定、切除後の適切な判断が必要となります。医療者も医療を受ける側も簡単・安易に考えるべきではないことを理解するべきです。したがって、「胃癌治療ガイドライン」に基づいた胃がんの進行度による治療適応の説明がなされ、同意を得る手続き(インフォームド・コンセント)の過程のなかで治療方針が選択されていくべきものです。
胃がんと告知された場合、以下の項目をしっかり確認しておく必要があります。
□術前の診断が早期胃がん、特に粘膜に限局したがんである可能性が高いか?
□生検による組織型が分化型がんであるか?
□病変の大きさは?
□病変の部位は?
□治療方法はEMRなのか? ESDなのか? 腹腔鏡手術なのか? 開腹手術なのか?
□内視鏡的切除であれば一括切除できるのか?
□治療のリスクは?(偶発症とその対策)
□内視鏡的切除後の病理組織結果は?(深達度、組織型、大きさ、脈管侵襲の有無、潰瘍の有無、切除断端など)
□最終的根治度は?(治癒切除、非治癒切除、判定不能)
□その後の治療方針は?(外科手術が必要なのか)
 図24 内視鏡的粘膜切除術(Endoscopic Mucosal Resection:EMR)
図24 内視鏡的粘膜切除術(Endoscopic Mucosal Resection:EMR)
 表3 胃がんの進行度に応じた治療法
表3 胃がんの進行度に応じた治療法